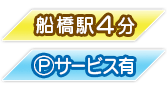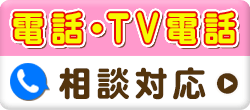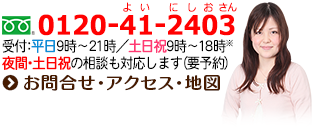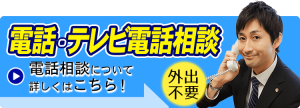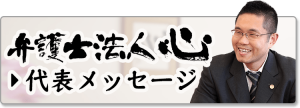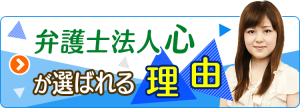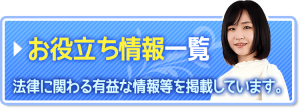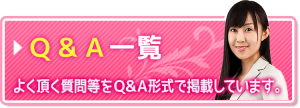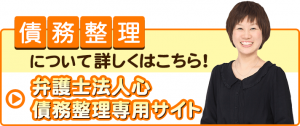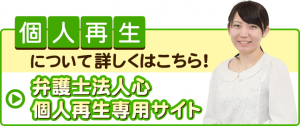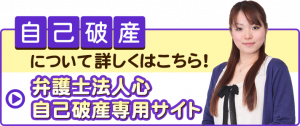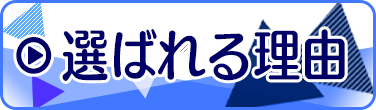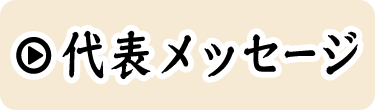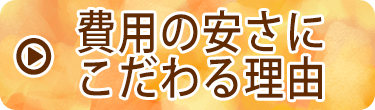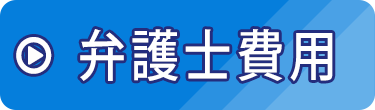任意整理ができる場合とできない場合
1 任意整理ができる場合とできない場合の概要
任意整理ができるか否かを分ける要素は、主に2つあります。
ひとつは、債務者の方が返済に回すことができる金額です。
任意整理をしても、返済を免れることができるわけではなく、月々の返済をする必要はあります。
任意整理をしても、月々の返済ができる見込みがない場合、任意整理はできないという判断をすることになります。
もうひとつは、任意整理前の返済条件です。
特に、一度債務整理をしている場合、任意整理をしても返済総額や月々の返済額を下げることができないということがあります。
以下、それぞれについて、詳しく説明します。
2 債務者の方が返済に回すことができる金額
一か月あたりの債務者の方の手取り収入から、生活上必要な支出を差し引いた金額が、月々の債務の返済に充てることができる金額となります(「返済原資」と呼ぶこともあります。)。
そして、任意整理の対象とする貸金業者等に対する債務額を、3~5年(36~60回)程度で分割した際の月々の返済額と、返済原資の金額を比較します。
月々の返済額が、返済原資の金額を下回っていれば任意整理は可能であると判断できます。
借入先が複数あり、かつ任意整理の対象としない貸金業者等がある場合には、その貸金業者等に対する月々の返済額と、任意整理の対象とする貸金業者等の任意整理後の月々の想定返済額の合計額が返済原資を下回っていれば任意整理はできます。
もし月々の返済額が返済原資の金額を上回る場合には、個人再生や自己破産を検討することになります。
3 任意整理前の返済条件
任意整理は、一般的には、残債額と遅延損害金を加えた金額を3~5年(36~60回)程度で分割して返済することになります。
そのため、既に一度任意整理をしていて、かつ分割回数が多いなど有利な返済条件となっている場合には、任意整理をしても効果が望めません。
また、貸金業者等によっては、元々金利が低く、かつ分割回数も多いなど、とても有利な条件で借り入れができているということもあります。
このような場合も、任意整理をしても月々の返済額や返済総額があまり変わらず、任意整理に要する費用が無駄になってしまう可能性もあります。